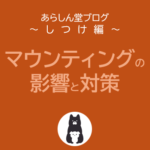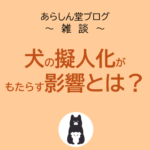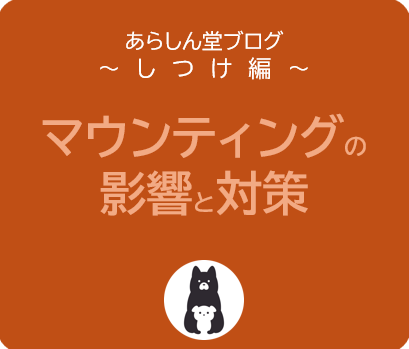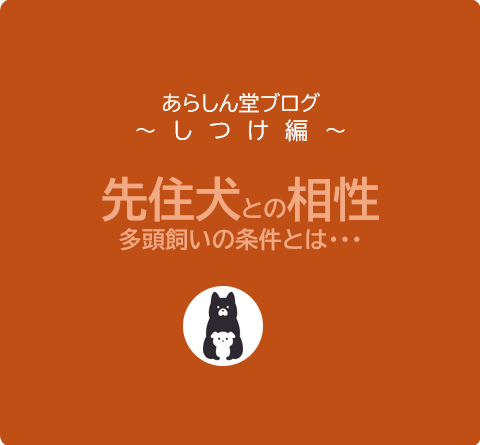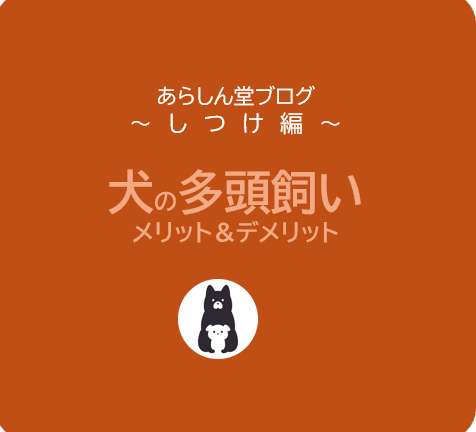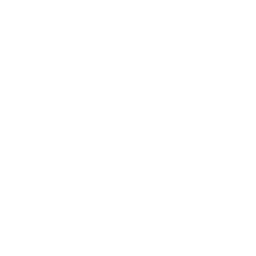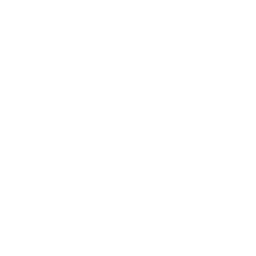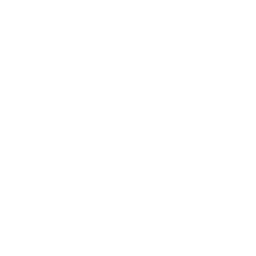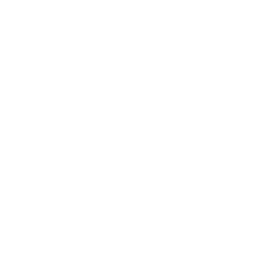犬がマウントされやすい理由と対策|性格・体格・社会性から読み解く行動学ガイド
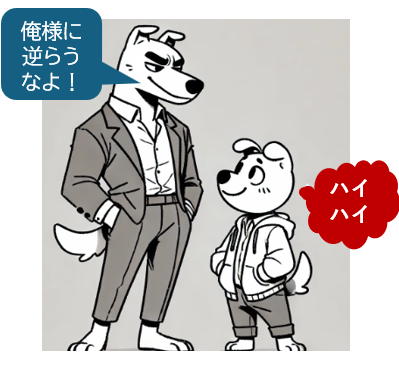
「うちの子、すぐに他の犬にマウントされてしまうんです…」
ドッグランや散歩中、そんなお悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。
犬同士の関係性の中で見られる「マウント行動」。一般的には「支配的な行動」と思われがちですが、実はそれだけではありません。遊びの一環、ストレス発散、ホルモンの影響など、背景にはさまざまな要因があります。
そして大切なのは、「マウントする側」だけでなく、「マウントされやすい側」にも特徴や理由があるということです。
この記事では、犬がマウントされやすい理由や特徴、そのリスク、そして具体的な対策を、行動学・心理学・実際の飼育体験を交えて詳しく解説していきます。さらに、わが家の愛犬「あられ」と「しんのすけ」の関係性から見えるリアルな事例も紹介します。
第1章|マウント行動とは?
1-1. マウントの基本的な定義
マウント行動とは、犬が他の犬や人、物の上に乗る行動を指します。特に犬同士では、後ろから乗る姿がよく観察されます。ですが、犬は必ずしも相手が犬でなくても構いません。クッション、ぬいぐるみ、飼い主の腕などに対してもマウントを取ることがあります。
1-2. 優位性のアピール
犬は群れで生活してきた歴史を持ちます。その中で、自分の立ち位置を示すために行うのが優位性アピールとしてのマウントです。これは「俺の方が上だ」というサインであり、犬社会における序列確認のひとつです。
1-3. 遊びや興奮の表現
一方で、マウントは必ずしも「支配」を意味するわけではありません。特に子犬や若い犬では、じゃれ合いの延長として軽くマウントすることがあります。これは遊びの一環であり、真剣な支配行動とは区別が必要です。
1-4. ストレスや不安の発散
犬は環境の変化に敏感です。引っ越しや来客、慣れない場所などでストレスや不安を感じたとき、マウント行動で気持ちを落ち着けようとする場合があります。人間が爪を噛む、貧乏ゆすりをするのと似た「自己安定行動」の一種です。
1-5. ホルモンの影響
未去勢のオス犬や、発情期のメス犬は、ホルモンによって性行動が強く出るため、マウントが増える傾向にあります。単純な支配行動とは異なり、生理的な要因が強く関わっているのです。
第2章|マウントされやすい犬の特徴
マウント行動を受けやすい犬には、いくつかの特徴があります。
2-1. 穏やかで控えめな性格
犬も人間と同じで、性格によって行動が変わります。穏やかで控えめな犬は、強気な犬からマウントされやすい傾向があります。逆らわず受け入れてしまうため、相手から「この子には乗っても大丈夫」と思われてしまうのです。
2-2. 社会性が未熟
子犬期に十分な社会化経験を積まなかった犬は、犬同士のルールや距離感を学んでいません。そのため、他の犬から「試される対象」になりがちです。これは「試し行動」の一環であり、社会性不足を補う必要があります。
2-3. 体格差
小型犬は大型犬に比べてマウントされやすい立場にあります。体格の違いによって、単純に「乗りやすい」という物理的な理由があるためです。トイプードルやチワワのような小型犬を飼っている方は特に注意が必要です。
2-4. ホルモンの影響
未去勢のオス犬は、他犬から注目されやすく、マウントされることも増えます。発情期のメス犬も同様で、「匂い」が他犬の関心を引き寄せます。ホルモンはマウントされやすさを大きく左右する要因です。
第3章|マウントされることによるリスク
マウントされても一見そんなに支障がないように思えますが、以下のような懸念があります。
3-1. 精神的ストレスの蓄積
犬は繊細な動物です。繰り返しマウントされることで「自分は弱い存在なのだ」と学習してしまい、ストレスが蓄積します。このストレスは吠え癖、食欲不振、下痢など、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。
3-2. ケガの可能性
大型犬にマウントされ、小型犬が転倒して関節を痛めるケースは少なくありません。体格差が大きい場合、頸椎や腰を傷めるリスクも高まります。特にシニア犬やパピーは要注意です。
3-3. 自尊心の低下と依存の増加
マウントされ続けると「自分では解決できない」と感じ、飼い主に依存するようになります。結果として自立心が育たず、常に飼い主に助けを求める犬になってしまうこともあります。
3-4. 社会性のゆがみ
犬同士の付き合いに消極的になり、ドッグランや散歩で他の犬を避けるようになる場合があります。これは「社会性の後退」となり、今後の生き方に大きな影響を与える可能性があります。
第4章|マウントされやすい犬を守る方法
マウントされやすい犬が自信を持ち、他の犬から狙われにくくするための具体的な方法をご紹介します。
4-1. 基本トレーニングで自信を育てる
「おすわり」「まて」「ふせ」などの基本コマンドを繰り返し練習させ、自信を育みましょう。自信のある犬は、他犬にマウントされにくくなります。
4-2. 遊びで主体性を強化
ボール遊びや引っ張りっこなどのアクティブな遊びを通じて、犬のエネルギーを発散させ、自主性を高めます。積極的に仕掛ける経験が、犬の自信を支えます。
4-3. 社会化体験を積む
安心できる犬仲間と遊ばせることで、犬同士のコミュニケーションを学べます。恐怖心が減り、他犬に堂々と対応できるようになります。
4-4. 飼い主の介入
マウントが続くときは、飼い主が冷静に間に入りやめさせましょう。強い叱責よりも、静かな制止とリードコントロールが効果的です。
第5章|犬種ごとのマウント傾向と性格差
マウント行動は「どの犬種でも見られる普遍的な行動」ですが、その出やすさや受けやすさには犬種ごとの性格や体格が大きく関わっています。
5-1. 和犬系(柴犬・甲斐犬・秋田犬など)
和犬は自立心が強く、誇り高い性格を持っています。そのため「自分が下に見られること」を極端に嫌う傾向があります。マウントされそうになると激しく反発し、相手を一喝して終わらせる場合も多いです。
→ このため「マウントされやすい」とは逆に、むしろ「させない」タイプが多いといえるでしょう。
5-2. テリア系(ジャックラッセル、ウエストハイランドホワイトなど)
テリアは活動的で好奇心旺盛。遊びの延長として他犬にマウントすることが多く見られます。特に若齢期には「とりあえずやってみる」行動が増えがちです。
5-3. トイプードル、シーズー、マルチーズなど小型愛玩犬
性格的に温和で人懐っこい犬が多く、他犬から強く出られると引いてしまう傾向があります。結果としてマウントされやすく、マウントの対象になりがちです。
5-4. レトリバー系(ラブラドール・ゴールデン)
社交的で遊び好き。マウントを「遊びの一部」として軽く行うケースが多いですが、悪意はなく、飼い主が正しく切り替えさせれば深刻な問題には発展しにくい傾向があります。
5-5. 超小型犬(チワワ・ポメラニアンなど)
体格のハンデからマウントされやすい立場になりがちです。しかしプライドが高く、意外と強気に反撃する子もいます。体格差による事故の危険があるため、特に注意が必要です。
第6章|わが家のケーススタディ
わが家には、中型犬の「あられ」(甲斐犬MIX)と、小型犬の「しんのすけ」(ジャックラッセルテリア)がいます。
しんのすけは元気いっぱいで、遊びの延長のようにあられにマウントを仕掛けることがあります。しかしあられは基本的に無視。堂々としており「そんなことをしても無駄よ」という態度を貫きます。
支配する意識の表れであるマウントのはずが、される方がまったく気にしない場合は効果はゼロです。もう、ただの、妖怪「子泣きじじい」状態・・・
ところが、しんのすけがあまりにも調子に乗ると、あられが本気で反撃に出ます。圧倒的な身体能力でひっくり返され、完全に制圧されるしんのすけ。その後しばらくは大人しくなり、マウント行動も控えめになります。
このエピソードからわかるのは、犬同士のやり取りの中にもバランスが存在しているということです。飼い主がすべて介入する必要はなく、時に犬自身に任せることで自然な学習が行われます。

第7章|よくある誤解と正しい知識
マウント行動について、飼い主さんの間でよくある誤解を整理してみましょう。
誤解1|マウントは悪い行動である
→ 実際には遊びの一部やストレス発散として自然に現れる場合が多く、「悪」と決めつけるのは早計です。大事なのは「状況を読み取ること」です。
誤解2|去勢すれば治る
→ 去勢は性ホルモンが関係するマウントには効果的ですが、遊びやストレス発散としてのマウントには影響が薄いです。去勢したのに行動が残る場合も珍しくありません。
誤解3|強く叱ればやめる
→ 犬にとってマウントは自然な行動。叱責で押さえつけると逆にストレスが溜まり、別の問題行動(吠え・破壊行動など)につながることもあります。
第8章|飼い主ができる具体的な対策
8-1. マウントを「やめさせたい」場合(する側の飼い主向け)
マウントを仕掛ける犬は、性格・ホルモン・ストレス・遊びの延長など、さまざまな理由で行動しています。飼い主がすべきことは「ただ叱る」ではなく、適切な代替行動を与え、マウント以外の方法で欲求を満たすことです。
ポイント1|十分な運動と発散
マウントは余ったエネルギーのはけ口になることがあります。散歩の時間を増やしたり、ボール遊びや知育トイで脳を使わせることが有効です。
ポイント2|基本コマンドで気持ちを切り替える
「おすわり」「まて」「おいで」を徹底して教え、マウントしそうになったらすぐにコマンドで別の行動に切り替えます。
ポイント3|ご褒美トレーニング
マウントせずに落ち着いていられたら、ご褒美を与えて強化しましょう。特におやつは即効性があり、「マウントよりも良いことがある」と学習させられます。
ポイント4|去勢・避妊を検討
性ホルモンが原因で頻繁にマウントする場合は、獣医師と相談の上で去勢・避妊を検討することも効果的です。
ポイント5|叱るよりも制御
強く叱っても根本解決にはなりません。リードを短く持つ、飼い主が体を間に入れるなど、物理的に行動を止めて「落ち着かせる」ことが大切です。
8-2. マウントを「されないようにしたい」場合(受ける側の飼い主向け)
マウントされやすい犬は、性格が控えめだったり、社会化が不足していたり、体格差が大きいことが原因になっていることがあります。飼い主は、犬に自信をつけさせ、相手に「狙われにくい存在」になってもらうことを意識しましょう。
ポイント1|自信を育てるトレーニング
「できた!」という達成感が犬の自信につながります。小さな成功を積み重ねることで、犬は堂々と振る舞えるようになり、他犬からマウントされにくくなります。
ポイント2|積極的な遊びで主体性を高める
飼い主との引っ張りっこやボールキャッチは、犬が自分から動く練習になります。「自分から行動できる犬」はマウントの対象になりにくいのです。
ポイント3|安心できる犬友達との交流
信頼できる犬仲間と遊ばせてポジティブな社会化を積ませましょう。犬は「自分もやれる」という成功体験を経て、苦手な相手にも動じなくなります。
ポイント4|飼い主のフォロー
マウントが続くときは、飼い主が間に入ってあげることも必要です。ただし守りすぎると依存を生むので、バランスが大切です。
ポイント5|体格差のある組み合わせを避ける
特に小型犬は大型犬にマウントされると大きなケガにつながります。遊び相手は体格が近い犬を選び、安全な環境で交流させましょう。
まとめ|2つのアプローチの違い
- する側:エネルギーの発散、代替行動の学習、ホルモン対策
- される側:自信をつける、主体性を育てる、安全な犬友達と交流
このように、アプローチは大きく異なります。「やめさせたい」「されないようにしたい」――どちらの立場から見るかで、取るべき方法が変わることを意識することが、マウント問題解決の第一歩です。
第10章|まとめ
犬のマウント行動は「問題行動」として片付けられがちですが、本来は犬にとって自然なコミュニケーションの一部です。
しかし、性格や体格差、社会化不足によって「マウントされやすい犬」が存在するのも事実。飼い主が正しく理解し、自信を育て、環境を整え、必要に応じて介入することが、犬の安心と幸せを守ります。
さらに、無添加のおやつを活用したポジティブ強化トレーニングは、犬にとって「楽しい学び」となり、ストレス軽減にもつながります。
マウントは「困った行動」ではなく、犬同士の関係性を映す鏡。飼い主がそれを読み取り、健全な方向へ導いてあげることで、愛犬の犬生はより豊かで安心なものになります。
第11章|あらしん堂のおやつでストレスケア
マウントされやすい犬は、ストレスや不安が溜まりやすく、結果として免疫力の低下や皮膚トラブルにつながることがあります。そんなときに役立つのが、無添加で栄養価の高い犬用おやつです。
あらしん堂では、毎日のトレーニングやリラックスタイムに活用できるおやつを多数取り揃えています。
- ぱきぱき秋鮭:オメガ3脂肪酸が豊富で、脳と心を落ち着ける効果が期待できます。マウントを抑えるトレーニング時の集中力アップにも。
- ころころマグロ:小粒で与えやすく、トレーニングのご褒美に最適。噛むごとに「できた!」という自信を強化できます。
- 馬アキレス:長時間噛めるため、ストレスを噛むことで発散できるナチュラルなおやつ。安心の無添加仕様です。
これらを使った「ご褒美トレーニング」は、犬にとって「楽しい学び」となり、マウント問題をポジティブに改善する大きな力になります。
👉 商品一覧はこちらからご覧いただけます:🔗 あらしん堂 犬用おやつ
また、あらしん堂でおやつを購入するだけで、身寄りをなくした可哀想なわんこ、にゃんこの救済に参加できます。是非、ご検討ください。
あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、 もう一度ぬくもりを。 売上の一部を保護犬・猫の支援に役立てています。
無添加おやつ・安全ケア用品で愛犬を健康に 保護犬・猫にもケアと新しい家族を おやつを買う2つ目の理由は愛のおすそわけ
「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?