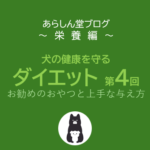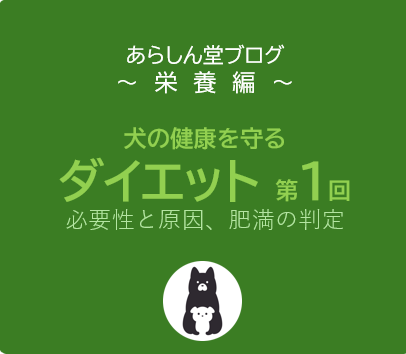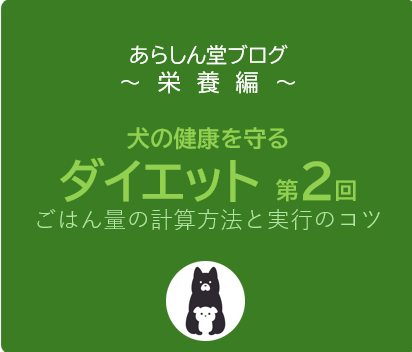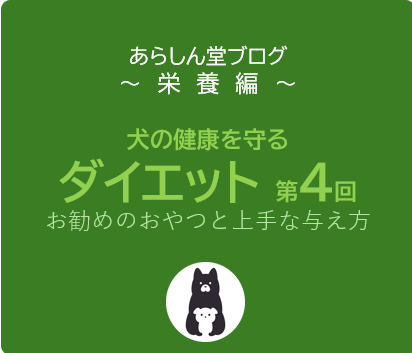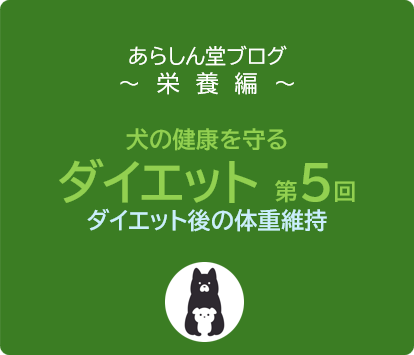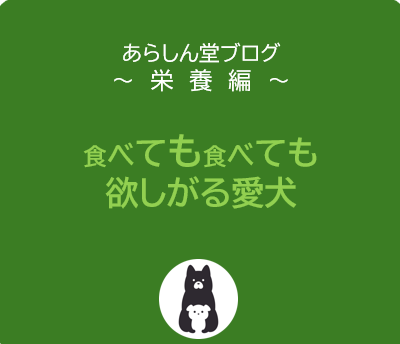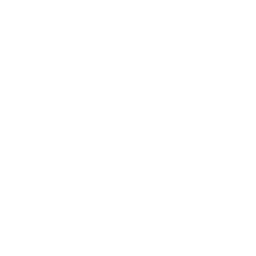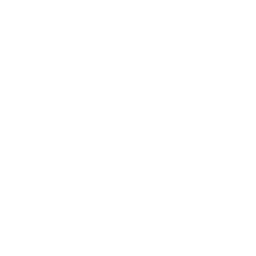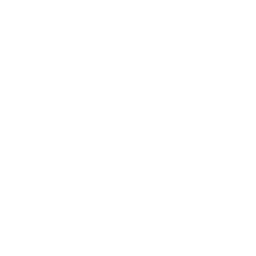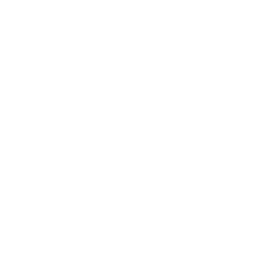愛犬の健康を守るためのダイエット(第3回/全5回)ダイエットの落とし穴
減量をするときには(人間と同じく)、運動する、野菜を増やす、減量用の総合栄養食を与えるなどのスタンダードなメソッドがあります。どれも間違ってはいませんが、どれにも弊害はあります。
特に「減量用 総合栄養食」の選択を誤るとまったくの逆効果になりますので、是非正確な知識をつけていきましょう。

運動する
太っているうちに運動させる場合、以下のようなリスクに注意する必要があります。
・関節や骨への負担が増加: 関節炎や股関節形成不全になることも
・心臓や呼吸器系への負担: 呼吸が荒くなり、心臓に過剰な負担も
・怪我をしやすい: 重い体を支える筋肉が十分でないため
・熱中症のリスク: 太っている=皮下脂肪が多いので体温調節が難しいため
これらのリスクは犬自身が相当辛く、運動嫌いになってしまうこともあるかもしれません。運動はあくまでも減量の進展に合わせて徐々に行いましょう。
野菜を増やす
人間の場合は野菜を増やすことはダイエットに有効ですが、犬の場合は注意が必要です。以下のような問題があります。
・消化能力の問題:
犬は野菜を消化する能力が低いので多めに与えると胃に負担をかけます。
・必要な栄養が不足:
犬に必要なタンパク質や脂肪といった主要栄養素が不足し、総合的な栄養バランスを崩すことがあります。
・カロリーの罠:
野菜でもジャガイモやサツマイモは炭水化物が多く高カロリーです。また、人参も糖質が多い食品です。
減量用の総合栄養食、怖い落とし穴
「減量用」と謳った総合栄養食でも、うかつに選ぶと逆に太りやすくなることがあるので、十分注意してください。減量用として、「低カロリー」のために、肉を減らすと以下のような状況となります。
■カロリー: 低い
カロリーの欄に小さい数値が書かれることは、その商品を購入する大きなモチベーションとなります。
■タンパク質、脂質:低い
肉を減らしたことでタンパク質、脂質は減少します。しかしながら、タンパク質量が減少すると筋肉が落ちます。
■糖質:高い
穀物を増やすと糖質が増加します。糖質を多く摂ることには、いくつかのリスクがあります。膵臓への負担や口腔内のトラブルなど。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
■不溶性の食物繊維が増加
穀物、野菜を増やすことで不溶性食物繊維が増えると、便の量が増えて空腹を感じやすくなります。空腹を感じやすいフードでは減量が難しくなります。
総合栄養食は「満遍なく栄養を取り入れたうえで、飼い主の悩み別に調節」しています。マーケティングが強いメーカーでは、肉を減らして野菜・穀物を増やせば、愛犬の肥満に悩む飼い主の心に響きやすいことを知っています。その結果、上記のように、減量には向かないフードになっていることがあります。
総合栄養食と療法食の違い
一方で、病院から指定される「療法食」があります。療法食は、医師から「病気である」と診断された犬に勧められるものです。つまり、治療が必要と判断され、それに対応するための最適な栄養が配合されています。
減量用療法食では、タンパク質は高めに、糖質は低めに、食物繊維も不溶性でなく、空腹感を抑える水溶性食物繊維を意識的に追加したりしています。
獣医に療養食を勧められた場合、療養食の値段が高いからと自己判断で市販の体重管理用総合栄養食を選択することは得策ではありません。
まとめ
せっかく愛犬の健康、長寿のためにダイエットを決意したのですから、それっぽい知識ではなく、飼い主は正確な知識をつけるべきです。特に体重管理用総合栄養食の逆効果は怖いです。深刻な肥満の場合は獣医の指示に従うことが大切です。
メール配信のご希望は
犬の栄養に関すること、しつけの方法など犬を幸せにする知識、その他ほんわかコンテンツをメールでもお送りします。
ご希望の方はこちらから「メール配信希望」としてお送りください!
犬に関するお困りごとにもお答えしますので、お気軽にお寄せください。