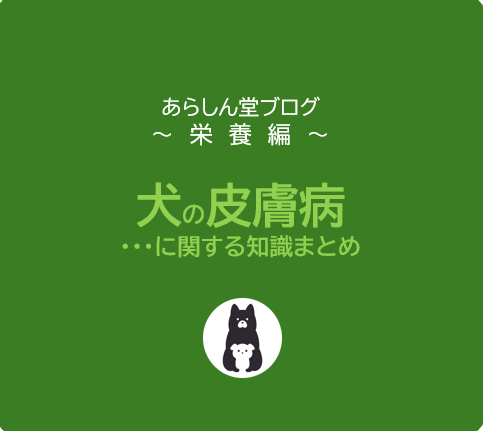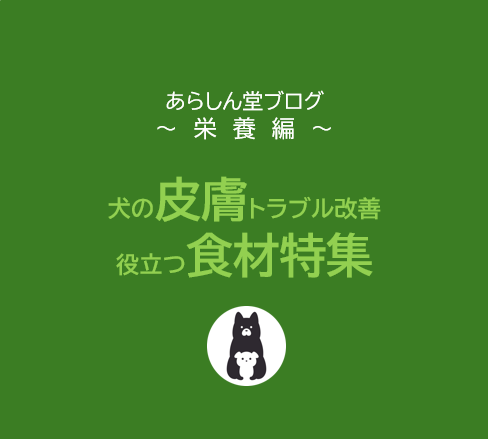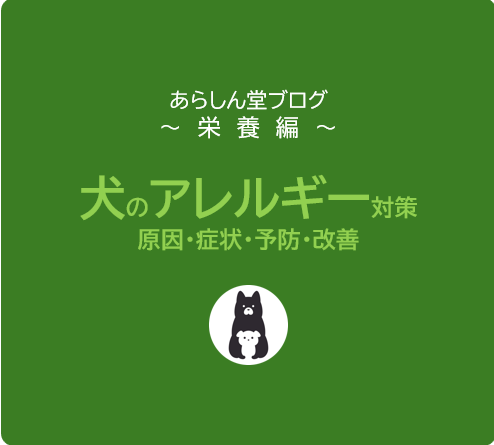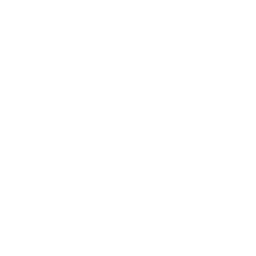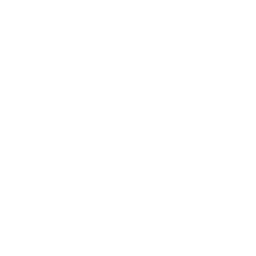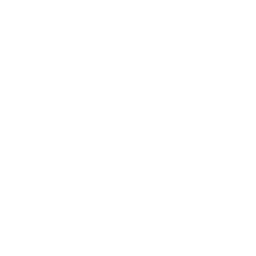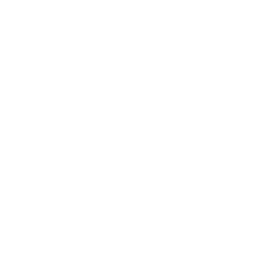犬のアレルギー完全ガイド|発症しやすい犬種・原因と食事・皮膚ケア・環境改善でできる対策まとめ

第1章|犬とアレルギーの関係性
犬と人間は数千年の歴史をともに歩んできました。その中で、犬の暮らしは大きく変化してきています。
かつては外飼いが一般的で、人間の食事の残り物を与えるのが当たり前の時代がありました。しかし、現代では犬は「家族の一員」として扱われ、室内で暮らし、栄養バランスを考えたドッグフードを与えられることが主流になっています。
こうした環境の変化は、犬の寿命を延ばすという大きな恩恵をもたらしました。一方で、生活の質が向上するにつれて増えてきたのが「アレルギー」です。
犬に増えるアレルギー
アレルギーとは、本来体を守るはずの免疫反応が過剰に働いてしまい、かゆみや炎症、消化不良などの症状を引き起こす状態を指します。人間と同じように、犬もさまざまなアレルギーを発症します。
特に近年は、
- 室内飼育による ハウスダストや花粉との接触増加
- 品種改良による 遺伝的な皮膚の弱さ
- 食生活の多様化による 食物アレルギーの増加
などが背景にあり、アレルギー症状を抱える犬が目立つようになっています。
アレルギーは「贅沢病」ではない
それでは、昔の犬はアレルギーなんてなかったのでしょうか。しかし、単に昔は気づかれなかっただけ、あるいは治療の概念がなかっただけという場合が多いのかもしれません。
実際には、昔の犬もかゆみや皮膚炎に悩んでいた可能性は高く、それが寿命を縮めていたことも考えられます。現代では犬のアレルギーのもとが増えた上に、犬の健康管理が進歩したことで、症状を「アレルギー」として正しく捉えられるようになったといえるでしょう。
アレルギーの影響は生活全般に及ぶ
犬のアレルギーは単なるかゆみだけではありません。慢性的な皮膚炎や耳の炎症はストレスとなり、生活の質を大きく下げます。消化不良を繰り返す犬では、栄養が吸収できずに体重が減ったり被毛の艶がなくなったりします。さらに、呼吸器系に影響する場合もあり、見過ごすと命に関わるリスクもあるのです。
飼い主ができる第一歩
大切なのは、飼い主が「犬も人間と同じようにアレルギーを発症する」という認識を持つことです。そして、症状が見られたときに「年齢のせい」「体質だから仕方ない」と済ませるのではなく、原因を探し、適切なケアを行うことが求められます。
愛犬の生活環境を整え、正しい知識を持って接することで、多くのアレルギーはコントロール可能です。犬も人間と同じようにアレルギーを発症することがあります。特に遺伝的にアレルギーになりやすい犬種が存在し、適切なケアをしないと皮膚トラブルや消化不良、呼吸器系の問題が発生することも。
今回は、アレルギーになりやすい犬種とその対策について解説します。
第2章|犬のアレルギーの種類と原因
犬のアレルギーは、原因となる物質(アレルゲン)により大きく分類されます。
それぞれの種類には特徴があり、症状の出方や対応方法も異なります。ここでは代表的な4つのアレルギーを詳しく見ていきましょう。
1. 食物アレルギー
犬に最も多いアレルギーの一つが「食物アレルギー」です。原因となる食品は多岐にわたり、代表的なものは以下の通りです。
- 牛肉、鶏肉、羊肉などの 動物性たんぱく質
- 小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物類
- 乳製品、卵、魚
中でも「牛肉」や「鶏肉」はドッグフードに広く使われる原材料のため、アレルギー反応を起こす犬が多いとされています。症状は・・
- 皮膚のかゆみ、赤み、フケ
- 嘔吐、下痢、軟便の繰り返し
- 慢性的な耳の炎症
食物アレルギーは皮膚症状だけでなく、消化器症状を伴うことが多いのが特徴です。
アレルゲンを特定するためには病院で検査するか、 「エリミネーションダイエット」(除去食試験)という方法があります。一定期間、特定の食材を排除した食事を与え、症状が改善するかを確認します。その後、一つずつ食材を加えて反応を見ていくことで、原因を突き止めます。
2. 環境アレルギー(アトピー性皮膚炎)
「犬のアトピー性皮膚炎」と呼ばれることもあり、生活環境の中にある微細なアレルゲンが原因となります。
- ダニ(特にハウスダストマイト)
- カビ(湿度の高い場所に多い)
- 花粉(スギ、ブタクサ、イネ科など)
- ハウスダスト、室内のホコリ
人間が花粉症に悩まされるのと同じように、犬も花粉やダニによってアレルギーを発症します。症状は・・
- 顔や耳、足先などのかゆみ
- 季節ごとに悪化(特に春や秋)
- 舐めすぎや噛みすぎによる脱毛
- 慢性的な皮膚炎
環境アレルギーは完治が難しく、「いかに症状を抑えながら生活するか」 がカギとなります。
掃除・換気・空気清浄などの環境整備が重要です。
3. 接触アレルギー
体の表面が直接触れるものによって起こるアレルギーです。
- シャンプーやリンスなどのケア用品
- 洗剤や柔軟剤の残留成分
- 化学繊維のベッドや洋服
- 新しい床材やカーペット
症状は・・
- 接触部分の皮膚の赤み、発疹、湿疹
- 特定の場所だけ症状が出る(例:首回り、腹部、足裏)
原因物質を避けることで改善が期待できます。低刺激のシャンプーや天然素材の寝具に切り替えることが効果的です。
4. ノミアレルギー性皮膚炎
犬に寄生するノミが吸血する際に注入する「唾液」がアレルゲンとなります。1匹のノミに刺されただけでも、重度のかゆみや炎症を引き起こすことがあります。症状は・・
- 激しいかゆみ(特に尾の付け根や背中)
- 皮膚が赤くなり、かさぶたができる
- 毛が抜けて脱毛斑ができる
ノミアレルギーは「ノミ対策の徹底」が最大の予防法です。定期的なノミ駆除薬の使用、寝具の洗浄、掃除機による環境管理が欠かせません。
第3章|犬種別に見るアレルギーのリスク
犬のアレルギーはすべての犬種で起こり得ますが、遺伝的要因や皮膚・被毛の特徴により、特に発症しやすい犬種が存在します。ここでは代表的な犬種ごとに「どんなアレルギーが多いのか」「どのような対策が必要か」を解説します。
フレンチ・ブルドッグ

フレンチ・ブルドッグは、その愛嬌たっぷりの表情とコンパクトな体型から人気が高い犬種です。しかし、皮膚が非常に敏感で、食物アレルギー、環境アレルギー、接触アレルギーのいずれも発症しやすい傾向があります。
特に顔や首にある「しわ」の部分は通気が悪く、湿気や汚れがたまりやすいため、細菌やカビが繁殖し炎症を起こしやすいです。
●よく見られる症状
- しわの間の赤みやただれ
- 耳のかゆみや炎症
- 下痢や嘔吐を繰り返す
●対策
- しわ部分を毎日清潔に拭く
- 低アレルゲンフードを選び、食事日誌をつける
- 通気性の良い寝床を用意する
ラブラドール・レトリーバー

人懐こく賢いラブラドールは、世界的に人気の高い犬種ですが、アトピー性皮膚炎を発症しやすい代表犬種です。特にダニや花粉などの環境アレルゲンに敏感です。
さらに皮脂の分泌が多いため、脂漏症(皮膚がベタつき臭いを伴う状態)と併発しやすい点も注意が必要です。
●よく見られる症状
- 耳の炎症(外耳炎)
- 脂っぽいフケや体臭
- 季節ごとのかゆみの悪化
●対策
- 定期的な耳掃除と低刺激シャンプー
- 花粉シーズンは散歩後に体を拭く
- 動物病院での早期検査と投薬管理
ゴールデン・レトリーバー

ゴールデン・レトリーバーは長毛で被毛量が多いため、花粉やホコリなどのアレルゲンが付着しやすい犬種です。また、食物アレルギーの報告も多く、皮膚のかゆみや炎症に悩まされやすい傾向があります。
●よく見られる症状
- 体を舐めすぎてできる脱毛
- フケや皮膚の赤み
- 消化不良による軟便
●対策
- 定期的なブラッシングで被毛に付着したアレルゲンを除去
- 食事はシンプルで無添加のものを選択
- シャンプー後は十分に乾かし、皮膚の蒸れを防ぐ
シーズー

シーズーは「皮膚病のデパート」と呼ばれるほど皮膚トラブルが多い犬種です。被毛が厚く、通気性が悪いため皮膚が蒸れやすく、細菌やカビの温床となります。涙やけも多く、目の周りが炎症を起こしやすい点も特徴です。
●よく見られる症状
- 涙やけによる赤茶色のシミ
- 耳や皮膚の湿疹
- 皮膚の赤みやかゆみ
●対策
- 目の周りを毎日清潔に拭く
- 被毛をこまめにトリミングして通気性を確保
- 保湿ローションで皮膚の乾燥を防ぐ
ダックスフンド

胴長短足で愛らしいダックスフンドは、食物アレルギーに敏感な犬種として知られています。特に小麦やトウモロコシといった穀物に反応しやすい傾向があります。
●よく見られる症状
- 繰り返す下痢や嘔吐
- 足先を噛みすぎて炎症
- 耳のかゆみ
●対策
- 穀物不使用(グレインフリー)のフードを試す
- アレルゲン食材を避けた手作りごはんを獣医師と相談のうえ実践
- 定期的に足裏や耳をチェックする
柴犬

日本犬である柴犬は、見た目は健康そうに見えても皮膚が非常にデリケートです。遺伝的にアトピー性皮膚炎を発症しやすく、特に季節の変わり目に症状が悪化しやすいとされています。
●よく見られる症状
- 顔や足先のかゆみ
- 乾燥によるフケ
- 季節ごとに悪化する皮膚炎
●対策
- 低刺激性シャンプーでのこまめなケア
- 室内の湿度を40〜60%に保つ
- 食事に魚由来のオメガ3脂肪酸を取り入れる
第4章|アレルギーのサインを見逃さない
犬のアレルギーは、突然重い症状として現れることもあれば、じわじわと進行して「なんとなく痒がっている」「よく耳を掻いている」といった小さな変化から始まることもあります。飼い主がそのサインを早期に察知し、原因を突き止めることが、症状の悪化を防ぐカギとなります。
ここでは、犬が示す典型的なアレルギーのサインを詳しく見ていきましょう。
1. 皮膚のかゆみや炎症
最もわかりやすいサインが「かゆみ」です。
- 足先や脇、顔をしきりに掻く
- 皮膚が赤くなり、湿疹やフケが出る
- 舐めすぎて毛が抜け、脱毛斑ができる
犬は言葉で「かゆい」と訴えることができないため、行動で示します。特に 体を床にこすりつける、同じ場所を執拗に噛むといった仕草が見られるときは要注意です。
2. 耳のトラブル
耳はアレルギー症状が現れやすい部位のひとつです。
- 外耳炎を繰り返す
- 耳をしきりに掻く、頭を振る
- 耳の中が赤く腫れ、悪臭がする
特にラブラドールやシーズーなど垂れ耳の犬種は通気性が悪いため、アレルギーから二次的に細菌やカビが繁殖しやすくなります。
3. 消化器症状
アレルギーは皮膚だけでなく消化器にも影響します。
- 慢性的な下痢や軟便
- 嘔吐を繰り返す
- 食欲があるのに体重が減る
食物アレルギーの場合、消化器症状と皮膚症状が同時に現れることも多く、「ただの食べ過ぎ」「胃腸が弱いから」と片付けないようにしましょう。
4. 涙やけ、目の症状
目の周りに赤茶色のシミ(涙やけ)が見られるのもアレルギーのサインのひとつです。
- 涙の量が異常に多い
- 目が充血している
- 涙やけで被毛が変色
シーズーやトイプードルなどは涙やけが出やすい犬種ですが、単なる体質ではなく、アレルギー反応や食事の影響が隠れていることもあるのです。
5. 呼吸器系のトラブル
環境アレルギーでは、まれに呼吸器に症状が出ることもあります。
- くしゃみや鼻水が続く
- 咳が出る
- 呼吸が浅く、ぜいぜいと音がする
花粉の多い季節や湿度の高い梅雨時期に悪化する場合は、環境アレルギーを疑うべきでしょう。
6. 行動の変化
アレルギーは身体的な症状だけでなく、犬の行動にも影響を与えます。
- 夜眠れず落ち着きがない
- かゆみに気を取られ遊ばなくなる
- イライラして攻撃的になる
犬が普段と違う行動を見せるとき、原因がアレルギーである可能性も考えられます。
●飼い主ができる観察の工夫
アレルギーの早期発見には「記録」が有効です。
- 症状が出た日付と状況をメモする
- 季節や天候との関連をチェックする
- 新しいフードやおやつを与えた場合は必ず記録する
これにより、獣医師に相談する際に的確な情報を伝えることができ、原因特定がスムーズになります。
第5章|食事によるアレルギー対策
犬のアレルギー対策において、最も大きな鍵を握るのが「食事管理」です。体の外から入ってくるアレルゲンの多くは口から取り込まれるものであり、適切なフード選びと栄養管理によって、症状を大きく和らげることができます。ここでは、具体的な食事の工夫と考え方を詳しく見ていきましょう。
1. アレルゲンになりやすい食材を避ける
犬の食物アレルギーでよく見られるのが、特定のタンパク質や穀物に対する反応です。代表的なアレルゲンは以下の通りです。
- 牛肉、鶏肉、羊肉、豚肉
- 小麦、トウモロコシ、大豆
- 乳製品、卵
「牛肉や鶏肉は犬にとって最も身近なたんぱく源」ですが、それだけにアレルギー反応が出やすいのも事実です。もし皮膚炎や消化不良の症状が見られる場合は、まずこれらの食材を疑ってみる必要があります。
2. 無添加、シンプルな食材を選ぶ
市販のドッグフードには、保存料・着色料・香料といった添加物が含まれるものも少なくありません。アレルギーを持つ犬には、できる限り無添加でシンプルな素材を使用したフードが適しています。
例えば、
- 原材料が「サーモンとポテト」など1〜2種類に絞られているフード
- グレインフリー(穀物不使用)のフード
- 原材料が国産・天然由来のフード
こうした選択が、アレルギーの負担を減らす第一歩となります。
3. エリミネーションダイエット(除去食試験)
食物アレルギーの原因を突き止めるためには、「エリミネーションダイエット」が有効です。
- アレルゲンの可能性が低いフード(例:サーモン単一タンパク源)を一定期間与える
- 症状の改善を観察する
- 改善が見られたら、元の食材を一つずつ追加し、反応を見る
この方法は時間と手間がかかりますが、アレルゲンを特定する確実な手段です。
4. 栄養素でサポートする
アレルギー体質の犬には、以下の栄養素が特に有効とされています。
- オメガ3脂肪酸(魚油・亜麻仁油)
皮膚の炎症を抑え、かゆみを和らげる効果が期待できる。 - 乳酸菌(プロバイオティクス)
腸内環境を整えることで、免疫バランスを改善しアレルギー症状を緩和。 - ビタミンE・C
抗酸化作用により、皮膚の健康維持や免疫力サポートに役立つ。 - 加水分解タンパク質
分子レベルで細かく分解されているため、免疫反応を起こしにくい。
5. 手作り食の注意点
「市販のフードは不安だから手作りに切り替えたい」という飼い主さんも多いです。確かに手作りごはんはアレルゲンを避けやすい反面、栄養バランスを崩すリスクもあります。
手作りを採り入れる場合は、以下に注意しましょう。
- 獣医師や栄養士に相談してレシピを決める
- カルシウムやミネラルの不足に注意
- 調味料や油は使わず、素材の味を活かす
6. おやつ選びも大切
フードに気をつけていても、実は「おやつ」が盲点になることがあります。市販のおやつには、小麦粉や添加物が多く含まれている場合があり、アレルギーを悪化させることも。
そのため、
- 単一素材のおやつ(例:乾燥魚、馬肉スティック)
- 無添加・無着色のおやつ
を選ぶことが望ましいです。
7. 水分補給の工夫
アレルギー体質の犬は皮膚の乾燥や新陳代謝の低下を招きやすいため、水分補給も重要です。
ドライフードにぬるま湯を加えてふやかす
ことで、消化を助けながら皮膚のうるおい維持にも役立ちます。
第6章|皮膚ケアとグルーミング
犬のアレルギー症状の多くは「皮膚」に現れます。かゆみ、赤み、湿疹、フケ、脱毛などは、犬にとって強いストレスであり、放置すると二次感染や慢性皮膚炎に発展することもあります。
食事と並んで大切なのが、日々の皮膚ケアとグルーミング(被毛・体のお手入れ)です。ここでは、具体的なケア方法を詳しく解説します。
1. 低刺激性シャンプーを選ぶ
アレルギー体質の犬には、刺激の強いシャンプーは大敵です。
- 合成香料や着色料が入っていないもの
- 硫酸系界面活性剤不使用のもの
- 保湿成分(オートミール、アロエ、ココナッツオイルなど)が配合されたもの
を選ぶのが理想的です。
●シャンプーの頻度
- かゆみが強いときは 週1回程度
- 落ち着いているときは 月1〜2回程度
皮膚を清潔に保つことと、洗いすぎによる乾燥のバランスをとることが大切です。

2. 保湿ケアの重要性
犬の皮膚は人間の約1/3の薄さしかありません。そのため乾燥しやすく、外部刺激に弱いのが特徴です。
シャンプー後は必ず保湿スプレーやローションを使いましょう。特に冬場やエアコンの使用時期は乾燥が悪化するため、日常的な保湿ケアが欠かせません。
3. 耳のケア
耳は湿気がこもりやすく、アレルギー症状が出やすい部位です。
- 耳の中を定期的にチェックし、赤みや臭いがあれば注意
- 専用のイヤークリーナーを使い、優しく拭き取る
- 綿棒は奥に押し込む危険があるため使用しない
ラブラドールやシーズーなどの垂れ耳犬種は特に要注意です。
4. しわのある犬種のケア
フレンチ・ブルドッグやパグのように顔や首にしわが多い犬種は、その間に湿気や汚れが溜まりやすく、細菌やカビが繁殖します。
- しわの間を清潔なガーゼやウェットシートで毎日拭く
- 拭いたあとは乾いた布で水分を残さないようにする
ちょっとした毎日の習慣で、大きな皮膚トラブルを防ぐことができます。
5. 被毛のケア
被毛は皮膚のバリア機能を助ける役割を持っています。
- 毎日のブラッシングで、毛のもつれを防ぎ、アレルゲン(花粉・ホコリ)を取り除く
- 換毛期は特に念入りに行い、通気性を確保
- 長毛犬種は定期的にトリミングして清潔を保つ
ゴールデン・レトリーバーなどの長毛犬種では、毛玉が皮膚トラブルの温床になるため注意が必要です。
. 肉球と足裏のケア
意外と見落とされがちなのが足裏や肉球です。
- 散歩後は必ず足を拭き、花粉やホコリを落とす
- 乾燥してひび割れがある場合は、犬用の保湿バームを塗布
- 舐めすぎる場合は、アレルギー症状のサインであることも
足裏は外部刺激を最も受けやすい部分なので、日々のチェックを習慣にしましょう。
7. 皮膚を清潔に保つ生活習慣
- ベッドや毛布は 週1回以上洗濯
- 室内はこまめに掃除機をかけてダニやホコリを減らす
- 加湿器で室内の湿度を40〜60%に保つ
皮膚ケアと環境整備をセットで行うことで、アレルギー症状は大幅に改善されやすくなります。
第7章|生活環境の整備と工夫
犬のアレルギーは、食事だけでなく「生活環境」に大きく左右されます。特に 環境アレルギー(アトピー性皮膚炎) は、犬が日常的に触れる空気、寝床、花粉、ダニ、カビなどが原因となるため、環境を整えることが重要です。ここでは、家庭でできる具体的な工夫を詳しく紹介します。
1. 寝床と生活スペースの清潔管理
犬は1日の大半を寝床で過ごします。そのため、ベッドや毛布にアレルゲンが溜まりやすく、症状の悪化につながります。
- 寝具は週1〜2回洗濯(できれば熱湯や高温乾燥機でダニを死滅させる)
- 中綿や布団は丸洗い可能なもの を選ぶ
- 部屋はこまめに掃除機をかけ、特にカーペットやソファなど布製品を清潔に保つ
小さな工夫の積み重ねで、犬の皮膚トラブルが軽減されるケースは多いです。
2. 空気環境の改善
犬のアレルギーに大きく影響するのが空気中のアレルゲンです。
- 空気清浄機:花粉やハウスダストを効率的に除去
- 換気:1日数回、短時間でも窓を開けて空気を入れ替える
- 加湿器:湿度を40〜60%に保ち、乾燥やカビの繁殖を防ぐ
特に梅雨や冬の暖房シーズンは、湿度管理が鍵となります。
3. 散歩後のケア
花粉やホコリは散歩中に犬の被毛に付着します。放置すると室内に持ち込まれ、アレルギー症状を悪化させます。
- 散歩から帰ったら 濡れタオルで体を拭く
- 足裏や肉球も丁寧に拭き、花粉を取り除く
- 被毛の長い犬はブラッシングをして毛に付いたアレルゲンを落とす
春や秋の花粉シーズンは、散歩の時間帯を花粉の飛散が少ない朝や夜に調整するのも効果的です。
4. ダニ・ノミ対策
犬の生活環境で最も厄介なのがダニやノミです。アレルギー体質の犬にとっては、1匹のノミに刺されただけでも強いかゆみを引き起こすことがあります。
- 定期的な駆除薬 の使用
- 布製品のこまめな洗濯と天日干し
- 掃除機でカーペットやソファの隙間を徹底的に掃除
これらを徹底することで、アレルゲンの数を大幅に減らせます。ダニ・ノミ対策はこちらのブログもご覧ください。
◆【保存版】犬のノミ・マダニ対策完全ガイド|正しい駆除と予防法で愛犬を守ろう!
◆ノミ・マダニ対策の決定版|スポットオン vs 内服薬の徹底比較と選び方ガイド
5. 室内の素材選び
アレルギーの犬には、生活空間の素材選びも工夫すると良いです。
- 床材:カーペットよりもフローリングやタイルが掃除しやすい
- 犬用ベッド:通気性の良い天然素材を選ぶ
- 洋服:ポリエステルなど化学繊維より、綿素材の方が低刺激
ちょっとした素材の違いが、皮膚への刺激を大きく変えることもあります。
6. ストレスケア
意外ですが、ストレスもアレルギー症状の悪化要因になります。ストレスがかかると免疫バランスが崩れ、皮膚炎や消化不良を起こしやすくなります。
- 規則正しい生活リズム
- 適度な運動と遊び
- 安心できる居場所を用意する
「心と体の健康」が整ってこそ、アレルギー症状も安定しやすくなります。
第8章|動物病院で受けられる検査と治療法
犬のアレルギーは、飼い主の工夫である程度コントロールできる部分もありますが、症状が重かったり長引いたりする場合は、必ず動物病院での診断と治療が必要です。ここでは、実際に病院で受けられる代表的な検査方法と治療法について詳しく解説します。
1. アレルギー検査の種類
●血液検査
犬の血液を採取し、特定のアレルゲンに対して抗体(IgE)がどの程度あるかを調べる方法です。
- 食物アレルギー、環境アレルギーの両方を検出可能
- 数十種類のアレルゲンを同時に調べられる
- ただし「疑陽性」「偽陰性」が出ることもあり、確定診断には使いにくい
●皮内反応試験
犬の皮膚にごく少量のアレルゲンを注射し、反応の有無を観察する方法です。
- 即時型の反応が確認できるため信頼性が高い
- 専門施設で行われることが多い
- 犬への負担がやや大きい
●除去食試験(エリミネーションダイエット)
最も確実な食物アレルギーの検査方法です。
- アレルゲンになりにくい食材だけを与える
- 数週間続けて症状が改善するかを確認
- その後、ひとつずつ食材を追加して反応を見る
検査には時間がかかりますが、確実に原因を特定できるのが強みです。
2. 薬物療法
●抗ヒスタミン薬:かゆみを和らげるために使用されます。
- 効果が出る犬と出ない犬がいる
- 副作用が比較的少なく安全性が高い
●ステロイド剤:強力に炎症を抑える薬です。
- 短期間で症状を改善できる
- 長期使用は副作用(免疫抑制、肝臓・腎臓への負担)が懸念される
●免疫抑制剤(シクロスポリンなど):免疫反応そのものを抑える薬です。
- 慢性的なアトピー性皮膚炎に効果的
- 高価で副作用もあるため、獣医師の管理が必須
●バイオ医薬品(オクラシチニブ、ロキベトマブ):近年注目されている新しい治療法です。
- オクラシチニブ(商品名アポキル):かゆみを速やかに抑える
- ロキベトマブ(注射薬):長期間効果が持続し、月1回程度の投与で管理可能
- 従来のステロイドより副作用が少ないとされる
3. 減感作療法
アレルギーの根本治療を目指す方法のひとつです。
- 犬のアレルゲンを特定し、ごく少量ずつ投与して免疫を慣らす
- 数か月〜数年かけて体質を改善する
- 即効性はないが、長期的にアレルギーを抑えることが期待できる
人間の花粉症治療で使われる「舌下免疫療法」と似た考え方です。
4. 外用薬とサプリメント
- 抗菌・抗真菌シャンプー:皮膚炎の二次感染を予防
- 保湿ローションやスプレー:皮膚のバリア機能をサポート
- サプリメント:オメガ3脂肪酸、乳酸菌、ビタミンEなど
薬物療法と併用することで、副作用を抑えながら症状改善を図ることができます。
5. 治療の考え方
アレルギーは「完全に治す」ことが難しい病気です。しかし、
- 適切な検査で原因を特定する
- 薬やサプリで症状をコントロールする
- 飼い主が食事や環境を管理する
これらを組み合わせることで、愛犬は快適に、そして健康的に生活を送ることが可能です。
第9章|飼い主からよくある質問(Q&A形式)
犬のアレルギーに悩む飼い主さんは多く、同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問を10項目ピックアップし、それぞれ詳しく解説します。
Q1. 犬のアレルギーは治りますか?
残念ながら、犬のアレルギーは完治が難しい病気 です。しかし、適切な食事管理・環境整備・薬物療法を組み合わせることで、症状をほとんど感じさせない状態にコントロールすることは可能です。
「治す」よりも「付き合いながら快適に生活させる」という視点が大切です。
Q2. アレルギーは遺伝しますか?
はい、アレルギー体質は遺伝的な要素を持つと考えられています。特定の犬種(フレンチブルドッグ、柴犬、ラブラドールなど)は特に発症リスクが高いです。繁殖においても、アレルギーの有無を考慮することが望ましいとされています。
Q3. 何歳くらいで発症することが多いですか?
犬のアレルギーは 子犬〜若齢期(6か月〜3歳ごろ)に発症するケースが多いです。ただし、中高齢になってから急に発症する犬も珍しくありません。年齢を問わず注意が必要です。
Q4. 手作りごはんにしたほうがいいですか?
手作りごはんは、アレルゲンを避けやすいというメリットがあります。ただし、栄養バランスが崩れやすい というリスクも。カルシウムやビタミン、ミネラルの不足は健康被害につながるため、獣医師や栄養士の監修のもとで行うことが望ましいです。
Q5. サプリメントは効果がありますか?
サプリメントは「治療薬」ではありませんが、補助的に役立ちます。
- オメガ3脂肪酸(魚油・亜麻仁油):皮膚の炎症を抑える
- 乳酸菌:腸内環境を整えて免疫バランスを改善
- ビタミンE・C:抗酸化作用で皮膚の健康を守る
ただし、個体差があるため、効果を実感できる犬とそうでない犬がいます。
Q6. 病院での治療は一生続けなければいけませんか?
アレルギーは慢性疾患なので、長期的な管理が基本です。ただし、症状が落ち着けば薬を減らしたり、中止できる場合もあります。重要なのは「定期的な健康チェック」と「無理のない治療計画」を立てることです。
Q7. かゆみがひどいときに家でできることはありますか?
- 体を冷たいタオルで軽く拭いて炎症を鎮める
- ノミやダニの寄生を確認し、必要なら駆除薬を使用する
- 環境を清潔に保ち、湿度を調整する
ただし、症状が強い場合は必ず病院で診てもらうことが必要です。自己判断で放置すると悪化してしまいます。
Q8. 散歩は控えたほうがいいですか?
花粉やホコリがアレルゲンになる場合、散歩は控えるのではなく工夫することが大切です。
- 花粉の少ない時間帯(早朝・夜)に行く
- 帰宅後に体を拭いてアレルゲンを落とす
- 室内遊びを増やし、運動不足を補う
散歩は心身の健康に欠かせないため、完全にやめる必要はありません。
Q9. シャンプーはどのくらいの頻度で必要ですか?
症状によって異なりますが、基本の目安は以下の通りです。
- かゆみが強い時期:週1回程度
- 安定している時期:月1〜2回程度
重要なのは低刺激性・保湿成分入りのシャンプーを使用すること。洗った後はしっかり乾かし、保湿ケアを忘れないようにしましょう。
Q10. 他の犬にアレルギーはうつりますか?
犬のアレルギーは感染症ではないため、うつることはありません。ただし、アレルギーによる皮膚の炎症に二次感染(細菌やカビ)が加わると、感染性皮膚炎として広がる可能性はあります。そのため、早めの治療が重要です。
第10章|まとめとあらしん堂の商品紹介
犬のアレルギー対策の本質
犬のアレルギーは、食物・環境・接触・寄生虫など多様な原因から引き起こされます。完治が難しい病気である一方で、食事管理、皮膚ケア、環境整備、動物病院での治療を組み合わせることで、症状を大きく抑えることが可能です。
飼い主が症状のサインを見逃さず、生活の中で「小さな工夫」を積み重ねていくことが、愛犬の健康寿命を延ばす一番の近道と言えるでしょう。
飼い主に求められる心構え
- 「ただのかゆみ」と軽視せず、早期に対応する意識を持つこと
- アレルゲンを避けるだけでなく、免疫力を高める生活習慣を整えること
- 獣医師と連携し、無理のない長期的な治療計画を立てること
アレルギーは「敵」ではなく「体からのサイン」です。飼い主の工夫と努力次第で、愛犬は快適に、そして幸せに暮らしていけます。
あらしん堂のこだわりと役割
アレルギー対策で最も大切なのは「口に入れるものの安全性」です。あらしん堂では、完全無添加、分かりやすい原材料にこだわった犬用おやつを取り扱っています。
- ぱきぱき秋鮭:良質なたんぱく質とオメガ3脂肪酸で皮膚と被毛をサポート
- 馬アキレス:低脂肪・高たんぱく、食物アレルギー対応に適したシンプルなおやつ
- ころころマグロ:消化にやさしく、アレルギー体質の犬にも安心
これらの商品は「余計なものを一切加えない」というポリシーのもと製造されています。アレルギー体質の犬でも食べやすく、健康管理の一助となるでしょう。
❤命をつなぐお買い物
あらしん堂は単なるペットフードショップではありません。
売上の一部を保護犬・保護猫の救済活動に寄付し、命をつなぐ活動を行っています。
- 健康的で安全なおやつを与えながら
- 保護動物の未来を支えることができる
それが「あらしん堂のお買い物」です。
犬のアレルギーは完治が難しいものの、飼い主が正しい知識を持ち、日々の生活で実践できる工夫を取り入れれば、十分にコントロールできます。
愛犬の「かゆい」「つらい」を少しでも和らげるために、
- 食事はシンプルに無添加で
- 皮膚と環境を清潔に
- 定期的に獣医師と相談
そして、安心して与えられる「ナチュラルなおやつ」を取り入れることが、愛犬の笑顔につながります。
👉 あらしん堂のおやつはこちらからチェックできます
あなたのお買い物が、保護犬や猫の命をつなぐ力になります。
あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、もう一度ぬくもりを。 あらしん堂では、売上の一部を保護犬・保護猫の支援に役立てています。 「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?